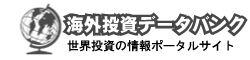 |
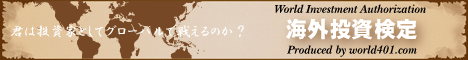
|
| 海外投資の基本 | 高度な投資戦略 | 為替リスク | 債券投資 | 国と企業の情報 | 株価指数&ETF | データ&用語集 | 確定拠出年金 |
|
国内ETFと海外ETFの違い〜どちらが有利?
海外投資は、分散投資の観点からも、低コストだという点でも、ETF(上場投資信託)を買う事がベターだということをお話ししてきました。 しかしETFを買う際には、二つの選択肢が考えられます。日本国内(東証・大証)に上場しているものを選ぶか、それとも海外市場(ニューヨークや香港)で上場しているものか・・・。そこで、どちらが有利なのかを比較分析してみました。比較は2011年10月時点の内容です。
売買手数料は国内ETFの方が安いのですが、当サイトで推奨している「長期投資」が前提の場合、より重視すべきコストは信託報酬の方です。売買手数料はその場限りのコストですが、信託報酬は毎年必ずかかるコストで、しかも資産が増えるほど負担額が大きくなっていくからです。一般的に、海外ETFの方が信託報酬は安いので有利といえます。 また、流動性リスクと信用リスクも考慮せねばなりません。この二つは、比較項目としてあまり意識されていませんが、非常に重要なポイントです。 流動性リスクとは、売買する人が少ない=出来高が小さい銘柄では、余分なコストが発生する事を意味します。株式はセリ形式なので、参加者が少ない場合は、買う時には割高に、売る時には割安にならざるを得なくなります(※注1)。国内上場の外国株ETFでは、出来高が非常に少ないものが多く、海外ETFに比べれば流動性リスクが高いのです。 カウンターパーティーリスク〜可能性は低いが最も恐ろしいもう一方の信用リスクについて。国内上場の外国株ETFでは、実際の株式を保有せず、保証元となる会社の社債等で構成され、その会社が株価指数との連動を保証する「リンク債ETF(別名:ETN)」というタイプがほとんどです。 例えば大証に上場している「上海上証50連動ETF【証券コード:1309】」では、組み入れ資産は「KBC IFIMA NV(ベルギーの銀行)」や「Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)」などとなっています(※注2)。リンク債型ETFというのは、これらの元資産会社がETFの価格を保証しているに過ぎないもので、これらの会社がもし破綻すれば、投資家にはお金が戻ってこない恐れがあるのです(カウンターパーティーリスクといいます)。 海外ETFのほとんどが、実際に投資対象となる株式を保有しています。また仮に、ETFを組成している会社が破綻しても、現物の株式を売却する事で、投資家にお金を返還する事が可能ですから、カウンターパーティーリスクは存在しません。 リンク債ETFに組み入れられる元資産は、ほとんどがヨーロッパの大手金融機関なので、破綻してお金が戻ってこないという可能性は、実際には低いと思われます。しかし、リンク債型がほとんどである国内ETFでは、このような余計なリスクを背負っている事は、ぜひ覚えておくべきです。リンク債型はこのデメリットがある反面、メリットは何一つありません。 以上、比較項目をまとめると明らかなように、海外ETFの方が国内上場のものよりも優れているといえます。長期投資を前提とするなら、多少面倒でも楽天証券
※注1:流動性不足から生じる売買ロスのことをスプレッド又はスリッページなどと呼びます。 |
海外投資のトラブルと対策 低PER投資の有効性 リバランスは必要ない! ドル円の一日の変動幅 ブラックマンデーの原因
国民年金基金のデメリット 上海総合指数 アメリカの長期金利 新興国債券は必要か?