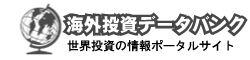 |
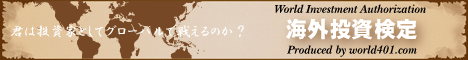
|
| 海外投資の基本 | 高度な投資戦略 | 為替リスク | 債券投資 | 国と企業の情報 | 株価指数&ETF | データ&用語集 | 確定拠出年金 |
世界のデフォルト経験国家の平均インフレ率
ギリシャや日本で財政破綻懸念が囁かれています。当サイトでも世界のデフォルト経験国一覧表を設けましたが、国民にとってより重要なのは、国家の破綻(国債の債務不履行)でどれだけ急激なインフレが起きるのか?という事でしょう。よって、デフォルト経験国では、平均的にどれだけ物価上昇があったのかをまとめてみました(※注1)。
※期間は1800〜2008年。標本数は国内債務214件、対外債務782件。 比較すると一目瞭然ですが、国内債務デフォルトの方が、対外債務デフォルトよりも高いインフレが起きています。理由は簡単で、国内向けの債務は新規に通貨を発行して返済できますが、外国への債務はそれが出来ないから(通貨発行を増やせば為替レートが減価⇒返済額は減らない)です。 しかし上記のデータは、1800年以降と非常に古いものも含まれており、また中南米やアフリカの小国のデータも多いです。その為、今後起きる危険性があるギリシャや日本のデフォルト⇒インフレ予測には不向きな面も多いです。また上記データの参考文献には、個別の事例については細かく記されてはいません。そこで、破綻国を1990年以降かつ、ある程度の経済規模を持つ国に絞って、当サイトで個人的にインフレ率データを収集してみました(※注2)。
ベネズエラや南アフリカなど、海外債務での破綻の場合は、前年に比べて発生年の方がインフレ率が下がっている国も見受けられますし、全体的にインフレも軽微なようです。一方、国内債務(対外と両方の場合も含む)では、やはりインフレ上昇率が高い傾向にあるようです。 国内で消化される国債はインフレで帳消しにされる?最後に、日本のデフォルト(1946年の新円切り替え&預金封鎖)前後のインフレ率です(※注3)。
残念ながら、戦時中の消費者物価指数データは残っていないようなので、デフォルト後のデータしかありません。そこで、データが現存する総合卸売物価指数の対前年比推移を参考に挙げておきます。 結論として、ギリシャがデフォルト財政破綻しても、国債の70%超が対外債務であることや、欧州統一通貨ユーロである事を考えると、数百パーセントといった高いインフレが発生する確率はほとんど無いでしょう。おそらく破綻しても、影響を最小限に抑える為、ECBやIMFがギリシャ支援(外貨=この場合はユーロを供給する)を行うと思われます。 一方、国債の約95%が国内消化である日本では、IMFが支援(外貨を供給する)する意味は全くありません。国債のデフォルト処理には、日銀が円を刷って国債を買い取るだけで済みます。その代償として、高いインフレが起きるでしょう。戦後の新円切り替え時の実例や、近年の他国の情勢を考えれば、インフレ率が100%(物価が2倍になる)を超えるような物価上昇が発生してもおかしくないと予測できます。 そうなれば、国債保有者は大きな損失を出すとともに、高いインフレが国民生活に悪影響が及ぼす事が予想されます。日本がデフォルトを避けるには、日銀が(米国のように)徐々に国債を買い取り、ソフトランディングさせる事が不可欠です。 ※注1:参考文献:「国家は破綻する―金融危機の800年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外投資のトラブルと対策 低PER投資の有効性 リバランスは必要ない! ドル円の一日の変動幅 ブラックマンデーの原因
国民年金基金のデメリット 上海総合指数 アメリカの長期金利 新興国債券は必要か?