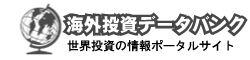 |
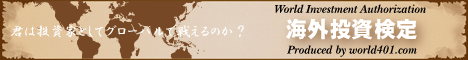
|
| 海外投資の基本 | 高度な投資戦略 | 為替リスク | 債券投資 | 国と企業の情報 | 株価指数&ETF | データ&用語集 | 確定拠出年金 |
債券の格付けは何処まで信頼できるか?
国債や大企業の社債などは、国内外の格付け会社がその安全性をレーティング(数値化・記号化)しています。世界には100社を超える格付け機関が存在しますが、実質的にマーケットに影響力を及ぼすのは、アメリカのS&P(スタンダード・アンド・プアーズ)とムーディーズ、イギリスのフィッチの3社です。S&Pは米国の平均株価=S&P500指数の、またフィッチはイギリスの平均株価=FTSE100指数の算出元でもあることから、日本でも有名です。 個人投資家は無論、機関投資家でさえも、逐一細かな財務分析をすることは難しいので、格付け会社のレーティングを参考にしています。現在の金融マーケットは、彼らに依存する比率が非常に高くなっています。 しかし格付け会社の信頼性には、常に疑問の声が上げられています。自社や利害関係者に有利に働くようレーティングを変動させているのでは?という点です。本当は安全であると判断して債券でも、自分たちが安値で買い付けたいが為にレーティングを格下げしている(その逆もしかり)、いわゆる仕手行為ではないのかという疑念です。 このように、格付け会社の信頼性を強く疑われるようになったのは、かのサブプライム問題の際です。大手三社はもとより、ほぼ全ての会社が、実際にはジャンク債同然であったサブプライム債券に、高いレーティングを付けていたことです。この件に関しては、サブプライム債券を売りたい金融機関とグルになっていたと言われても、弁論の余地はありません。 下の表(※注1)は、2007年初頭から2008年末に、ムーディーズのサブプライム債券の格付けがどの位置まで下がったかを表します。横軸で示しており、右に行くほど低レートであることを意味します。最高格がAaa(いわゆるトリプルA)で、Caは破綻寸前・ほぼデフォルトの状態を示し、Cは既に破綻した債券となります。
例えば2007年初頭にAaaであったサブプライム債券のうち、2008年末にもAaaであった割合は10.9%で、Aaに下がったものが3.8%、破綻であるCにまで至ったものは10.9%あったということです。Aa(ダブルエー)の債券だと、94%がデフォルトに陥ったことになります。二番目に高かった債券ですら、たった2年で94%が破綻した訳です。サブプライム債券に関する格付けが、如何に信頼できないものであったのかは、これを見れば一目瞭然です。 危機時の格下げは現実よりも遅れるまた、自分たちの利害に基づいて失敗したのではなく、本当に危険を見抜けず、不適切なレーティングを行っていたケースも多々あります。例えば2001年に破綻したエンロン社(※注2)について、格付けは常に後手に回りました。エンロン社債を投資不適格レベルへ格下げしたのは、倒産のわずか4日前でした(S&P・ムーディーズ共に)。実際に関連会社まで詳細に調査していれば、もっと早く危機を察知できたかもしれないので、評価能力の欠如と言われても仕方ないでしょう。 そして記憶に新しいギリシャの債務隠蔽問題でも、格付け会社はそれを見抜けていませんでした。S&P・ムーディーズ・フィッチとも、2009年末までギリシャ国債を投資適格にけしており、それを「投機的レベル」にまで格下げしたのは2011年。ギリシャ政府の隠れ債務が公に発覚したのが2010年1月ですから、随分後のことでした。そして、ギリシャの長期金利が急上昇したのは、ムーディーズがジャンク債認定した2011年7月以降です。 つまり、安全とされる対象が危機に陥った際、格付けは現実より遅行する事がほとんどです。危機を事前に格付けに反映させることは、非常に難しいのです。ですから現在トリプルAであろうと、絶対安心とは言えないのです。 ましてや、マーケットはレーティングの変更どおりに左右されるとも限りません。2011年8月5日に、S&Pが米国債を一段階引き下げ、史上初めてトリプルA格を失いました。しかし、アメリカの長期金利は逆に低下し、7月末に2.8%だったものが8月中旬には2%割れ寸前にまで買いが集まりました。企業の決算発表などと同じで、マーケットが格下げを織り込み済みであれば、実際の債券価格は上昇(長期金利が低下)することもありえるのです。 我々一般の投資家は、債券投資は「長期に安全運用するもの」だという基本を守ることが先決です。確かに債券マーケットは、格付けの変更により乱高下する場合があります。しかし、彼らが公正中立ではないこと、また彼らの危機察知能力は十分でないことを理解し、細かな変動を気にせず、長期スタンスでの投資を厳守すべきです。 ※注1:参考文献「経済は格付けで動く(黒沢義孝:著)」。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外投資のトラブルと対策 低PER投資の有効性 リバランスは必要ない! ドル円の一日の変動幅 ブラックマンデーの原因
国民年金基金のデメリット 上海総合指数 アメリカの長期金利 新興国債券は必要か?